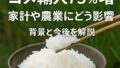税負担を軽くしたいあなたへ|別居の親も「扶養控除」の対象になる条件とは?
「親が別居していると、扶養控除は受けられない」と思っていませんか?
年々上昇する社会保険料や税金に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。 とくに30代~50代の方は、子育てや住宅ローン、そして親の介護や支援など、家計の負担が重くのしかかってきます。
そんななか、知っておくだけで税金が軽くなる可能性があるのが「扶養控除」です。 扶養控除と聞くと「子ども」が対象と思われがちですが、実は別居している「親」も条件を満たせば対象になります。
本記事では、特に「親が別居中」の場合でも扶養控除が認められる条件や注意点について、税務署でも確認される重要なポイントを踏まえて丁寧に解説していきます。 税金の節約をしたい方、年末調整や確定申告での申請を考えている方はぜひ最後までご覧ください。
扶養控除の基本と「親」を対象にする条件
そもそも扶養控除とは?
扶養控除とは、納税者が家族などを扶養している場合に所得税・住民税が軽減される制度です。 主に「所得が少ない家族を支援している人の税負担を軽くする」目的で設けられています。
親も対象になるが、所得条件あり
扶養控除の対象には配偶者や子どもだけでなく、親や祖父母などの「直系尊属」も含まれます。 ただし、「所得が48万円以下」という要件があります。
年金受給者の親であれば、65歳以上で年金のみの収入の場合、年金収入が158万円以下であれば扶養控除の対象になります。 この「158万円以下」という金額は、年金からの所得計算に基づくラインです。
別居でもOKなケースが増えている
「同居していないと扶養にできない」と思われがちですが、実は「生計が同一」であれば、別居していても控除の対象になります。 生計同一とは、日常的に仕送りをしていたり、生活費や医療費などの負担をしている場合です。
つまり、遠く離れて暮らしている親であっても、実際に金銭的支援をしているのであれば、扶養控除の対象にすることができます。
別居の親を扶養控除に入れるための具体的要件
要件1:親の所得が48万円以下(年金収入のみなら158万円以下)
扶養控除を受けるには、親の年間所得が48万円以下であることが前提です。 これは「給与収入」だけでなく、「年金収入」も対象になります。
65歳以上の親の場合、公的年金控除が適用されるため、実質的には年金収入158万円以下であれば扶養に入れる可能性があります。
要件2:送金記録(生活費や療養費など)の証明が必要
別居している親を扶養控除の対象にするには、「生活費や療養費を負担していること」を証明する必要があります。 具体的には、親の口座へ振り込んだ記録(振込明細や通帳のコピーなど)を保存しておくとよいでしょう。
現金手渡しの場合は証明が難しいため、できるだけ銀行振込など記録が残る方法を選ぶことが推奨されます。
要件3:「生計同一」の判断基準
生計同一とは、「経済的につながりがある状態」のことを指します。 別々に暮らしていても、継続的に生活費や医療費の援助をしていれば認められます。
たとえば、毎月一定額を送金している、医療費を支払っている、介護サービス費を負担しているなどの事例が該当します。
ケーススタディで学ぶ|扶養控除の適用例
例1:月5万円の仕送りをしている遠方の親
東京都内に住む会社員のAさんは、地方に住む母親に毎月5万円を送金しています。 母親の年金収入は150万円で、65歳以上です。
この場合、母親の所得は48万円以下に該当し、かつ仕送りの証明もあるため、扶養控除の対象になります。
例2:老人ホームに入所中の親を支援しているケース
Bさんの父親は高齢者施設に入所中で、Bさんが月10万円を施設費として支払っています。 父親の収入は遺族年金のみで、その他の所得はゼロです。
遺族年金は非課税扱いのため、父親の所得はゼロ。 この場合も送金の事実が明確であれば、扶養控除を受けられます。
例3:親が要介護認定済で障害者控除も対象の場合
Cさんの母親は要介護2の認定を受けており、自治体の障害者手帳はないものの、介護認定で「特別障害者」に該当。 月に4万円を仕送りしています。
この場合、扶養控除に加えて「障害者控除」も適用できる可能性があります。 障害者控除を受けるには、介護認定区分による「障害者認定書類」の提出が必要となるので、自治体で発行を受けましょう。
年末調整・確定申告の手続き方法
会社員の場合:「扶養控除等申告書」の記入
年末調整の際に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に、親の氏名や生年月日、住所などを記入します。 別居であることを明記し、生計同一である旨も備考欄などに記載しておくとスムーズです。
フリーランス・自営業の場合:確定申告で申請
確定申告書Bの第二表「扶養親族」欄に親の情報を記載します。 扶養控除の金額を自動計算するソフトも多いため、e-Taxなどを活用すると便利です。
控除証明や送金記録の保管ポイント
税務署からの問い合わせに備え、振込明細や通帳コピー、医療費の領収書などを5年間は保管しておくのが安心です。 特に現金での支援は証明が難しいため、振込が推奨されます。
扶養控除と併用できる「障害者控除」との違い
障害者控除の活用で控除額アップ
親が要介護認定を受けており、障害者控除の対象になる場合は、扶養控除に加えてさらに控除が増えます。 特別障害者控除なら、所得税で40万円の追加控除が受けられることも。
70歳以上の親なら「老人扶養親族」として控除額アップ
70歳以上の親を扶養している場合、「老人扶養親族」として通常の扶養控除(38万円)より多い48万円(同居老親等なら58万円)の控除が適用されます。
よくある間違いと税務署対応事例
・送金の証明が不十分(現金手渡し) ・年金収入の額を誤って記入 ・生計同一の確認資料がない といったケースで扶養控除が否認されることがあります。 申告前に資料をそろえて、税務署の問い合わせにも対応できるようにしましょう。
まとめ|親が別居でも、扶養控除で税金を軽くできる
扶養控除は、同居していない親でも条件を満たせば適用できる「節税の強い味方」です。 ポイントは、親の所得が48万円以下であること、生活費などを定期的に支援している記録があることです。
また、年齢や障害の状態により、老人扶養控除や障害者控除などの制度とも併用できます。 毎年の年末調整や確定申告を丁寧に見直すことで、家計の負担をぐっと軽くするチャンスが広がります。
「知らなかった」ではもったいない税制優遇。 ぜひこの機会に、あなたの親の支援が正しく税務上でも評価されるよう、扶養控除の申請にトライしてみてください。